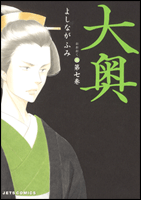テレビドラマ「大奥 ~誕生~ 有功・家光篇」 第1話感想
2012年10月12日より始まった、TBS系列の金曜ドラマ「大奥 ~誕生~ 有功・家光篇」。
今回よりテレビドラマ版の終了まで、その流れと原作からの改変要素について追っていきたいと思います。
今回は10月12日放映分の記念すべき第1話の感想です。
なお、当ブログでは前作映画および原作版の「大奥」についても色々と書いております↓
前作映画「大奥」について
映画「大奥」感想&疑問
実写映画版とコミック版1巻の「大奥」比較検証&感想
原作版「大奥」の問題点
コミック版「大奥」検証考察1 【史実に反する「赤面疱瘡」の人口激減】
コミック版「大奥」検証考察2 【徳川分家の存在を黙殺する春日局の専横】
コミック版「大奥」検証考察3 【国内情報が流出する「鎖国」体制の大穴】
コミック版「大奥」検証考察4 【支離滅裂な慣習が満載の男性版「大奥」】
コミック版「大奥」検証考察5 【歴史考証すら蹂躙する一夫多妻制否定論】
コミック版「大奥」検証考察6 【「生類憐みの令」をも凌駕する綱吉の暴政】
コミック版「大奥」検証考察7 【不当に抑圧されている男性の社会的地位】
コミック版「大奥」検証考察8 【国家的な破滅をもたらす婚姻制度の崩壊】
コミック版「大奥」検証考察9 【大奥システム的にありえない江島生島事件】
第1話のストーリーは、コミック版「大奥」2巻の最初からP107までの話をなぞったものとなっています。
後に「お万の方」となる有功が、本物の家光の代わりとして擁立された女版家光と出会うまでの物語です。
最初は前作映画「大奥」の続きで、徳川8代将軍吉宗が没日録を読み始めるところから始まるのではないかと予想していたのですが、それはなかったですね。
前作映画では「暴れん坊将軍」的な演出もあったわけですし、吉宗にも友情出演程度くらいの出番はあるかと考えていたのですが(^_^;;)。
内容を見る限りでは、これでもかと言わんばかりに原作のストーリーどころか描写までも忠実に再現している感がありましたね。
コミックを片手に作中の描写を比較してみても、登場人物がしゃべっているセリフも、その場その場におけるシーンでの姿勢などもほぼ同じでしたし。
原作と違うシーンと言えば、江戸城の屋敷に閉じ込められた有功と玉栄と明慧の3人が屋敷から一時的に脱走したことと、原作にはあったレイプやセックスの描写が軒並み省略されていたことくらいでしょうか。
まあ後者については、PG-12やR-15指定も可能な映画と異なり、テレビドラマではその手の描写を描きたくても描けない状態にあるのですから、当然と言えば当然の措置ではあるのでしょうけど。
配役を見てみると、個人的には春日局が原作よりも若く、かつ何か違う印象を受けましたね。
原作の春日局は髪が白髪なのですが、テレビドラマ版の春日局は黒髪で、それだけでかなり若いイメージが付きまといましたし。
一応春日局は、史実でも寛永20年9月14日(1643年10月26日)に死去しており、第1話終了時点(寛永17年(1640年)夏)で既に老齢かつ余命3年程度しかないのですから、ここは白髪でも良かったのではないかと思えてならなかったのですが。
登場人物の姿形はもちろんのこと、明慧が澤村伝右衛門に斬られる描写までそっくりそのまま再現しているほどだったのに、春日局だけ何故黒髪に変えてしまったのか、少々疑問なところではありますね。
ひょっとすると、後の話で白髪にして「老い」を表現するという演出でもするのかもしれませんが、それにしても「3年程度でそこまで変わるのか?」という違和感が伴わざるを得ないでしょうし。
ところで春日局と言えば、ラスト付近で原作には全くなかった面白い設定をのたまっていましたね。
曰く「御三家に男子がいない」と。
こんなことは原作の春日局は全く述べてなどいませんでしたし、テレビドラマ版同様に春日局に相談を持ちかけられた松平伊豆守信綱も、これまた春日局の「徳川の血を絶やさぬために……」云々のスローガンに対して「春日局が残したいのは徳川家の血というより、彼女が溺愛した家光公の血筋なのではないか?」という疑問を抱いています。
松平伊豆守信綱がこんな疑問を抱くのも、家光の血筋以外に徳川御三家やその他の傍流の「徳川家の血を引く存在」がいるからに他ならないからでしょう。
だからこそ私も、コミック版「大奥」検証考察2【徳川分家の存在を黙殺する春日局の専横】で、件の春日局の対応の問題点を指摘していたわけですし。
では今回、改めて追加された「徳川御三家に男子はいない」は果たして正しいのか?
徳川御三家というのは、江戸幕府の開祖たる徳川家康の9男・10男・11男を始祖とする徳川分家のことを指します。
その始祖の生没年を調べるだけで、この春日局の発言が全くの大嘘であることがすぐに分かってしまうのです。
徳川御三家の始祖の生没年は以下の通り↓
尾張藩の尾張徳川家 始祖・徳川義直
生誕 慶長5年11月28日(1601年1月2日)
死没 慶安3年5月7日(1650年6月5日)
紀州藩の紀州徳川家 始祖・徳川頼宣
生誕 慶長7年3月7日(1602年4月28日)
死没 寛文11年1月10日(1671年2月19日)
水戸藩の水戸徳川家 始祖・徳川頼房
生誕 慶長8年8月10日(1603年9月15日)
死没 寛文元年7月29日(1661年8月23日)
1634年に家光が赤面疱瘡で死んだ時点では当然3者全てが生存しており、かつ彼らは全員家光よりも年上なので、彼らが赤面疱瘡を患う可能性は家光のそれよりもさらに低いと言わざるをえないでしょう。
特に水戸徳川家に至っては、その成立自体が1636年なので、それ以前の時点で始祖たる徳川頼房が死んでしまうと、下手すれば家の存在自体が歴史から消滅してしまうことにもなりかねません。
そして、徳川御三家が創設されたそもそもの目的が「宗家存続」にある以上、将軍位に何かがあった場合は自家の存続や相続よりもそちらが何よりも優先されなければならないのも自明の理というものです。
徳川御三家の始祖が生存している以上、最悪の場合は彼らの中の誰かが徳川将軍になりさえすれば良く、「徳川御三家に男子はいない」云々の発言は何ら成立することがないのです。
何故春日局は、こんなすぐに誰にでも分かるウソなんてついてしまったのですかねぇ。
徳川御三家のお家事情なんて、江戸城に参内する武士であれば誰でもすぐに分かる程度の情報でしかないでしょうに。
この辺りの設定、後日のエピソードでフォローされることがあったりするのでしょうかねぇ。
コミック版「大奥」でさえ、徳川御三家は家光の時代には全く言及すらされていないというのに。
設定面では1話目の段階で早くもミソがついてしまった感がありますが、「原作の忠実度」という点ではなかなかのものがあるのではないかと。
次回予告では有功が素振りをやっているシーン・白猫の若紫、それに玉栄が大奥の男衆に対して「殺してやる」と呟くシーンが出てきますが、ストーリー自体はどこまで進むことになるのやら。