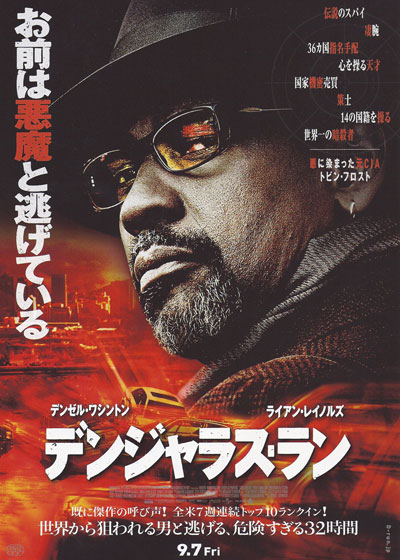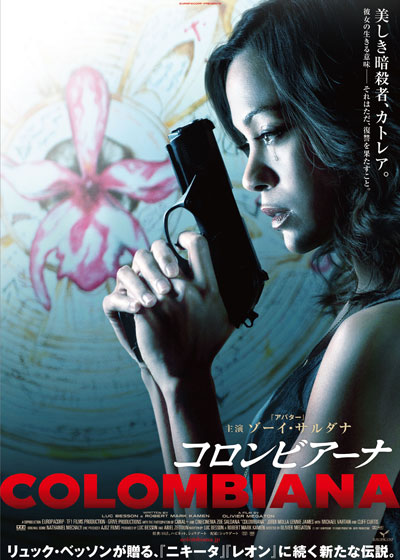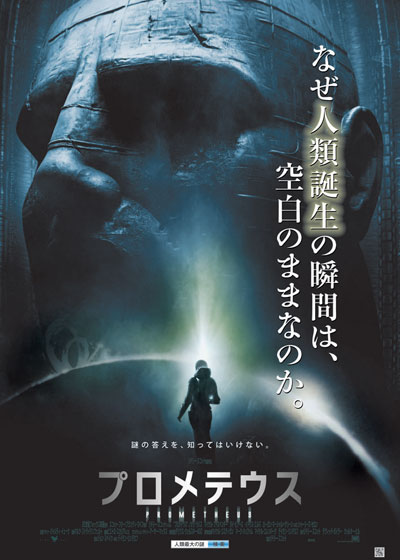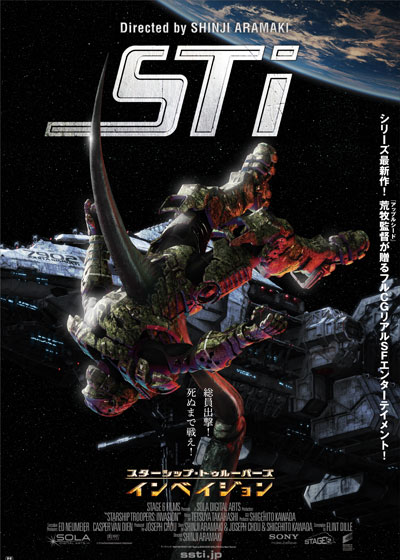映画「ハンガー・ゲーム」感想
映画「ハンガー・ゲーム」観に行ってきました。
アメリカで大ベストセラーとなった、スーザン・コリンズの同名小説を原作とするサバイバル・スリラー作品。
今作ではストーリー構成上、血みどろの殺し合いや死体の描写が少なくないことから、PG-12指定されいます。
現在のアメリカ合衆国?の崩壊後に誕生したらしい、近未来の独裁国家パネム。
パネムは首都であるキャピトル、および周囲を取り巻く複数の地区によって成立しており、キャピトルに居住する少数の富裕層が、周囲の地区の労働者達を奴隷同然に酷使するという支配体制を築き上げていました。
そんな不平等な支配体制を、支配される側であるキャピトル周囲の地区が不満に思わないわけもなく、彼らはキャピトルおよび中央政府に対してしばしば暴動や反乱が引き起こされていました。
中でも、75年以上前に勃発した13地区の一斉蜂起は、第13地区の完全崩壊および多数の犠牲者を出すという結果にまで至っていました。
この反乱の鎮圧後、パネムの中央政府は、壊滅した第13地区以外の12の地区に対する懲罰的な措置と、自分達自身の娯楽を満たすことを目的とする「ハンガー・ゲーム」という名のビッグイベントを開催することを思いつきます。
「ハンガー・ゲーム」とは、件の反乱に参加していた残り12の地区から、12~18歳までの若い男女2人ずつを選出させ、総計24名の男女を最後のひとりになるまで戦わせるという、一種のサバイバルゲームです。
生存確率は24分の1、ただし勝者には一生遊んで暮らせるだけの富貴と名誉が与えられる「ハンガー・ゲーム」は、以後、年1回のペースで実に73年にわたって開催され続けてきました。
そして映画の冒頭では、新たに開催される予定の第74回「ハンガー・ゲーム」に向けての男女選出が行われようとしている渦中にありました……。
炭鉱が盛んな第12地区で貧しい生活を営んでいる、今作の主人公カットニス・エバディーン。
炭鉱夫だった父親を亡くした過去を持つ彼女は、幼い妹のプリムローズ・エバディーンを何かと気にかけつつ、生計の足しにすべく弓矢を使って狩猟をする生活を送っていました。
しかし、第74回「ハンガー・ゲーム」は、そんなささやかな生活を送っていたカットニスの人生をも一変させてしまうことになります。
第12地区における第74回「ハンガー・ゲーム」のくじ引き選考で、彼女の妹であるプリムローズがゲームの女性出場者として選出されてしまったのです。
問答無用で連れ去られようとしたプリムローズを助けるべく、カットニスは無我夢中で自分が第74回「ハンガー・ゲーム」に出場すると宣言します。
何でも「ハンガー・ゲーム」への出場に自分から志願するケースは、すくなくとも第12地区では初めてだったらしく、カットニスの志願はあっさりと受け入れられます。
一方、第12地区における第74回「ハンガー・ゲーム」の男性出場者は、カットニスの級友で、かつてカットニスが生活苦で飢えていた際にパンを恵んでくれたピータ・メラークが選出されました。
母親および妹に「必ず帰ってくる」と告げ、カットニスは第74回「ハンガー・ゲーム」に参加すべく、ピータと共にパネムの取得キャピトルへと向かうことになるのですが……。
映画「ハンガー・ゲーム」の原作小説は、その設定の相似性から日本の小説「バトル・ロワイアル」との関連が以前から指摘されています。
何しろ両作品には、
1.舞台が近未来の独裁国家で、強権的な支配体制が構築されている。
2.ある程度まとまった数の10代男女の未成年者達が、最後のひとりになるまで殺し合いに狂奔するサバイバルゲームを主軸にしている。
3.ゲームフィールドは広大だが限定された空間で、かつゲーム主催者による監視が常にありとあらゆる手段を駆使して行われている。
などといった共通項があるのですから。
かくいう私自身、映画の予告編を見た際には「これってアメリカ版バトル・ロワイアル?」という感想を抱いたくらいですし(^^;;)。
もっとも、原作者であるスーザン・コリンズ自身は「原作のハンガー・ゲームを出版するまで、バトル・ロワイアルの存在自体知らなかった」と述べてはいるのですが。
ただこういうのって、実際には参考にしていたとしても「これは俺のオリジナルだ!」と言い張ることが珍しくもないですし、作中の設定やストーリー展開に少なからぬ共通点や類似性が多いことからも、やはり何らかの関連性は疑わざるをえないものがあります。
まあ真実は原作者のみ知るところではあるのですが、果たして真相は如何なるものなのやら。
かくのごとく「バトル・ロワイアル」が何かと引き合いに出される映画「ハンガー・ゲーム」なのですが、ただ実際に映画を観る限りでは「確かに設定面における共通項は少なくないが、ストーリー展開では明確な違いも存在する」というのが正直なところではありましたね。
たとえば、「バトル・ロワイアル」で生徒達に支給されていた武器には銃火器や爆弾の類も少なくなく、アクション映画ばりの銃撃戦が行われることすらあったのに対し、「ハンガー・ゲーム」のゲームフィールドで提供される武器はナイフや弓矢など原始的なものばかりです。
作中の「ハンガー・ゲーム」では地雷は登場していたのですが、銃火器はとうとう一度も出てくることはなく、各出場者達は最後までナイフや弓矢などの武器を使った戦いに終始していました。
また、「バトル・ロワイアル」と比べてゲームの開催期間が長く、単純な戦闘能力だけでなく原始的な生活能力までもが試される場となっており、出場者同士による戦いだけでなく、猛毒の木の実などを食べて出場者が死んだりするケースなども披露されていたりします。
「バトル・ロワイアル」では時間が経つにつれて、入ったら即首輪が爆発して死ぬ「侵入禁止エリア」が増えていき、行動範囲が狭められていくというルールがあったのですが、「ハンガー・ゲーム」にそのようなルールは特にありません。
ただその代わりとして、安全圏に居座ろうとする出場者を、ゲーム主催者側が仮想空間のゲームフィールドをいじって強引に叩き出すという行為を行ってはいましたが。
何よりも一番違うところは、「バトル・ロワイアル」の参加者達がある日突然、それも必要最小限の説明だけで問答無用でさっさと戦場に放り込まれるのに対し、「ハンガー・ゲーム」の出場者達は充分な準備期間を置いてゲームが始められる、という点ですね。
「バトル・ロワイアル」では「今自分達がどのような状況に置かれているのか」ということすら理解しえずに殺されていった参加者達が、特に序盤では少なくなかったですし、理解しても甘い認識のまま殺される参加者が後を絶たなかったものでしたが、「ハンガー・ゲーム」にはそのような出場者は最初からおらず、ゲーム開始直後から誰もが覚悟を決めて殺し合いなり逃亡なりを初めていましたから。
個人的には、「ハンガー・ゲーム」よりも「バトル・ロワイアル」の方が、生死を争うサバイバルゲームとしては合理的に出来ているように見えましたね。
「バトル・ロワイアル」はゲームシステム的に参加者同士による殺し合いが自動的に発生せざるをえないようになっているのに対し、「ハンガー・ゲーム」はゲーム主催者が事あるごとにいちいち介入しないと、参加者同士の遭遇および戦闘がなかなか発生しないルールになってしまっているのですから。
そもそも、原則非公開の「バトル・ロワイアル」と違い、「ハンガー・ゲーム」は全国民に生中継される一種の「国民的イベント」でもあるのですから、ゲーム主催者による介入が常に目に見える形で行われるというのは、エンターテイメント的な観点で見てさえもマイナスにしかならないのではないかと思うのですけどね。
作中では自分達の都合から、「勝者はひとりのみ」というルールそれ自体を勝手に変更したり、かと思えば撤回したりまた復活させたりと、二転三転なルール改竄が平気で横行していましたし。
あのシステムでは、「ゲーム主催者による八百長」が疑われても仕方のない要素が少なくありませんし、エンターテイメントや掛け試合としても成立し難い一面が否定できないのではないかと。
あと、ゲームの勝者として生き残れる者は一人しかいないにも関わらず、勝つために徒党を組む者達の間で心理的な駆け引きがないなど、やや不自然な設定が少なくないですね。
生き残る確率を上げるために、さし当たっては徒党を組んで多数で少数を圧倒する、という行為自体は、「バトル・ロワイアル」でも「ハンガー・ゲーム」でも共通して見られた現象です。
しかし、ゲームのルール上「勝者(生存できる者)はひとり」でしかない以上、徒党を組んだ者達の間では、「自分はいずれ裏切られるのではないか?」「ならば先手を打ってこちらから裏切るべきではないのか?」といった深刻な不信感が芽生えてもおかしくはないんですよね。
徒党を組んだメンバーで他の勢力を圧倒した後は、徒党を組んだメンバー同士で戦いが始まるのは誰の目にも最初から明らかなのですから。
「勝者(生存できる者)はひとり」というルールの中で徒党を組むという行為は、戦闘力で他者を圧倒しえる反面、自分がいつ寝首をかかれるか、逆に自分が仲間達を殺す機会を常に伺うなどという二律背反的な状況およびそれに伴う葛藤を招くことになるわけです。
しかし「ハンガー・ゲーム」では、その手の葛藤が全くと言って良いほど描かれていなかったりするんですよね。
「ハンガー・ゲーム」で徒党を組んでいた面々は、ただその戦闘力に物を言わせて殺戮を楽しんでいただけでしたし、仲間達を疑うようなピリピリした雰囲気すら全くないありさま。
それは主人公であるカットニスにも言えることで、成り行きで彼女が第11地区出身の少女ルーと手を組んだ際、彼女もルーも「2人が最終的に生き残ったら2人で殺し合いをしなければならない」という可能性を全く考慮していないとしか思えない言動に終始していました。
ルーと同じく第11地区出身の黒人男性などは、殺されたルーの仇を討ち、あまつさえ「ルーが世話になったから一度だけだ」とカットニスをわざわざ逃がす行動に走ってさえいましたし。
参加者全員が顔見知りである「バトル・ロワイアル」と違い、「ハンガー・ゲーム」で顔見知りと言えるのは、よほどの偶然でもない限りは同じ地区の出場者だけなのですから、もう少し感情を排した打算的な殺し合いが展開される方が、むしろストーリー展開としては却って自然なのではないかと思えてならなかったのですが。
この点においても、「バトル・ロワイアル」の方が「ハンガー・ゲーム」よりも構成が上手いのではないかと。
ただ、あまりにもエグい描写や設定が目白押しの「バトル・ロワイアル」をある意味【ぬるく】したような「ハンガー・ゲーム」は、それ故に一般受けしやすいものにはなっていると思います。
かくいう私も、途中からは結構「安心して観賞できた」クチでしたし(^^;;)。
映画「ハンガー・ゲーム」は、既に続編の製作と日本公開が決定しているとの情報が、映画のエンドロール直前にて披露されています。
その点から言えば、今作は「シリーズ1作目」として観賞するのも良いかもしれません。