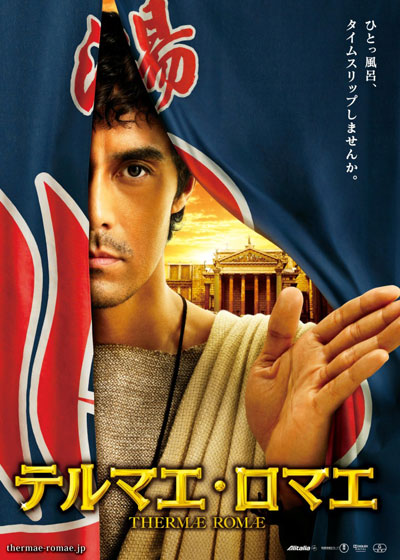映画「臨場 劇場版」感想
映画「臨場 劇場版」観に行ってきました。
横山秀夫のミステリー小説を原作とし、テレビ朝日系列で放映された人気ドラマシリーズの劇場映画版。
今作はテレビドラマシリーズの続編という位置付けではありますが、ストーリー自体は映画単独で成り立っており、テレビドラマ版から引き続き出演している主人公含めた登場人物達の人間関係以外は、これまでのシリーズを知らなくても問題なく観賞可能です。
かく言う私も、テレビドラマ版はただの1話も観賞することなく今作に臨んでいましたし(^^;;)。
映画の冒頭は、大雨が降り注ぐ無人の街中で、今作の主人公にして「終身検視官」の異名を持つ倉石義男が倒れ込むシーンから始まります。
このシーンの意味するところが何なのかについては物語後半である程度明らかになりますが、序盤は思わせぶりに明示するだけで次のシーンへと移行します。
次に映し出されるシーンは2010年冬の吉祥寺の繁華街?における、如何にも平和的な広場を普通に行きかう人々の姿。
そんな一般的な光景は、しかし突如突っ込んできたバスの中から慌てて下車して悲鳴を上げて逃げ惑う人々と、血塗れになってナイフを握りながら狂笑を浮かべるひとりの男によって、唐突に終わりを告げることになります。
ナイフを持った男は、広場にいた通行人達に無差別に切りつけていき、さらにその場にいた2人の女性を刺殺までしてしまいます。
ナイフの男こと波多野進は、バスの中でも2人の人間を殺害、さらに15名もの重軽傷者を自らの手で作り上げており、彼は複数の警察官によってその場で現行犯逮捕されます。
ここで倉石義男は、事件の現場検証で部下達と共に遺体の検視を行うと共に、遺体と遺族の対面にも立ち会うことになります。
ところが波多野進はその後、警察の事情聴取の場で精神喪失状態の様相を呈したことで刑法39条の1「心神薄弱者ノ行為ハコレヲ罰セズ」の規定が適用され、一審・二審共に裁判で無罪判決が下されることになってしまうのでした。
当然のごとく、遺族は波多野進に対する理不尽な無罪判決に怒りを抱くことになるのですが……。
それから2年後。
東京都港区で弁護士事務所を営んでいる高村則夫が、事務所内で何者かに殺害されるという事件が発生します。
検視官である倉石義男も当然のごとく遺体の検視を命じられることとなり、彼は最初、部下である小坂留美に検視の実務を委ね、自身は遺体の着衣や遺品などを調べ始めます。
そこで倉石義男は、ズボンに濡れている痕跡があることを発見することになります。
それを不審に思った倉石義男は、ある程度進んでいた小坂留美の検視を制止し、自分で直接遺体をつぶさに調べていくのでした。
倉石義男が小坂留美に検視を任せる際は常に最後までやらせるのに、と同じく倉石義男の部下である永嶋武文は呟いています。
その後の司法解剖では、直腸温の測定に基づいた遺体の死亡推定時刻が割り出されるのですが、倉石義男は肝臓の温度測定による死亡推定時刻が直腸温測定のそれと比べて数時間のズレがあることを発見、遺体に何らかの細工が行われているのではないかという疑問を抱きます。
さらにその後、今度は神奈川県警の管轄で病院を営む精神科医・加古川有三が殺害されるという事件が発生します。
遺体の傷跡に高村則夫との共通点が浮かび上がったことから、警察はこの2つの事件が同一犯の犯行によるものと断定、警視庁と神奈川県警との間に合同捜査本部が立ち上がることになります。
高村則夫と加古川有三が、2年前の無差別通り魔事件の際に波多野進の弁護と精神鑑定をそれぞれ担っていたことから、神奈川県警の捜査一課の管理官・仲根達郎は、裁判での判決に不満を抱いた遺族の犯行によるものと断定し、遺族について調べるよう捜査官達に指示を出します。
しかし、遺族に医学的知識を持つ者がいないことを理由に「俺のとは違うなぁ」と仲根に異を唱える倉石義男。
2人が対立する中、さらに捜査線上には全く別の線から出てきた容疑者の存在も浮上し始め……。
映画「臨場 劇場版」では、理不尽な犯罪や冤罪で身内を失ってしまった遺族の悲哀と、さらにその立場から容疑者として疑われる理不尽な様子が描かれています。
元来娘がいるはずもない場所で突然娘を失ってしまった母親の関本直子や、神奈川県警の捜査ミスで冤罪を着せられた挙句に自殺してしまった息子の助けられなかったと自分を責め続ける父親&現職警察官の浦部謙作などは、本来ならば事件の被害者もいいところだったはずです。
しかし警察からは、まさにその立場故に犯行を行っても不思議ではないと逆に目をつけられ、それを前提とした事情聴取や監視を受けることにまでなってしまうんですよね。
特に浦部謙作などは、物語終盤で「アレだけ警察に奉仕してきたのに、息子を奪った次は自分なのか!」と怒りを露にし、当時の冤罪事件の捜査責任者だった仲根達郎を自身の手で殺害しようとした挙句、最終的には自身の拳銃で自殺してしまうのですからね。
実際に彼は連続殺人事件の犯人では全くなかったわけで、そんな気は全くなかったにせよ、結果として無実の人間にあらぬ疑いをかけ死に追いやることになってしまった警視庁管理官・立原真澄は、さぞかし甚大なショックを受けざるをえなかったことでしょうね。
結果的に彼は、浦部謙作の息子を自殺に追い込んだ仲根達郎と全く同じ過ちを犯してしまったことになるのですから。
物語中盤頃の立原真澄は、冤罪事件で仲根達郎を責めるかのごとき言動を繰り広げていたのですが、まさかそれが自分にも跳ね返ってくることになるとは夢にも思わなかったことでしょうね。
もちろん、仲根達郎にしても立原真澄にしても、別に明確な悪意を持ってあの親子を冤罪に陥れようとしたわけでも何でもなく、あくまでも事件解決を心から願い正義感を持って行動した末の悲劇ではあったのですが。
この辺りは、全知全能ならぬが故の、警察というよりも人間の限界ではあるのでしょうが、それだけに被害者はもちろんのこと、捜査官達の苦悩や後悔もやるせないものがありますね。
作中の展開で少し疑問に思ったのは、物語終盤における波多野進についてですね。
彼は事件の遺族の墓参りから措置入院している病院に戻ってきた際、浦部謙作から2発の銃弾を受け、さらに連続殺人事件の真犯人である安永泰三に注射までされてしまい、今まさに生命を奪われんとしていたのですが、それを止めに入った倉石義男と安永泰三が対峙している間に奇跡的な復活を遂げ、安永泰三を刺殺した上に倉石義男にまで襲い掛かっているんですよね。
2発の銃弾(しかもそのうち1発は左胸から左肩の間付近に命中している)+注射を受けてなお、そこまでの行動に打って出られること事態が凄まじく驚異的であると言わざるをえないところなのですが。
あの注射って、最初は筋弛緩剤のような類の致死性薬物で、注射された時点で波多野進はもう死んだものとすら考えていたくらいでしたし、アレだけ劇的な復活を遂げたとなると麻酔という線も確実にないでしょう。
状況的に見てあまりにもありえない劇的過ぎる復活だったために、安永泰三は興奮剤かエンジェルダスト(PCP)の類でも間違って注射してしまったのではないかとすら考えてしまったほどです(^_^;;)。
また波多野進は、措置入院における自分の更正が全くの偽りであることを倉石義男の前で自白したりしているのですが、倉石義男に凶器を取られてしまった途端に再び精神異常者の演技を繰り出しているんですよね。
その前の言動を見てそんなことをしても騙される奴はまずいないでしょうし、そもそもあの状況における波多野進であれば、倉石義男が投げ捨てた凶器を拾うなり、安永泰三が持っていたナイフを奪い取るなりして反撃する術も体力もまだ充分に余力を残していたのではないかと思うのですが。
それどころか、あの驚異的な復活ぶりから考えると、下手すれば素手でも倉石義男を殺すことが可能だったのではないかとすら思えるくらいですし(苦笑)。
ゲームのバイオハザードに出てくるゾンビクラスの生命力を、あの時の波多野進は持ち合わせているようにさえ見えたくらいですからねぇ(^^;;)。
どの道、波多野進にしてみれば、自身の精神異常者としての振る舞いが全くの演技であることの目撃者である倉石義男を殺さなければ、自身の弁明を周囲に信じ込ませることもできないわけですし、足掻ける限りの物理的な抵抗をしても不思議ではなかったくらいなのですが。
あの重傷からの復活も奇跡かつ驚異的ならば、あそこで抵抗を止めてしまうというのも多大な違和感を覚えざるをえないところでして。
あと、今作ではエンドロール後に重要な映像が出てきます。
もぬけの殻になった倉石義男の自室に置かれている携帯電話が鳴り響き、連絡主の小坂留美が倉石義男と連絡が取れないことに絶望的な表情を浮かべる、というものなのですが、これが実は土砂降りの雨の中で倒れこむ冒頭の倉石義男の描写と結びついていたりするのでしょうか?
いかにも続編が出そうな終わり方ではあるのですが、これって一体どうなるのでしょうかねぇ。
いずれにせよ、今作ではエンドロールが完全に終わるまで席を立たないことを是非ともオススメしておきます。
テレビドラマ版からのファンはもちろんのこと、ミステリー好きな人達にも単品で満足できる作品であると言えますね。